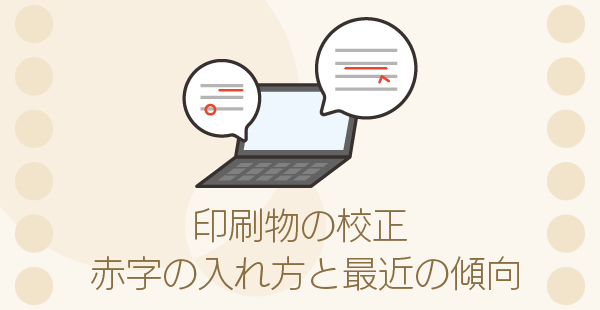印刷物を作るとき、どんなに急いでいても飛ばしてはいけない「校正」というステップ。
チラシ、パンフレット、ポスター…どんなものでも、入稿前にしっかりとチェックすることが大事ですね。
この「校正」という作業、昔と今ではやり方がだいぶ変わってきています。
「みんなはどうやって校正しているの?」「どんなふうに伝えたらいいの?」と思っている発注担当者さんに向けて、最近の校正事情についてお話してみたいと思います。
昔の校正は「紙に赤字」でした
少し前までは、プリントアウトした紙に赤ペンで書き込みをして、修正指示を出すのが一般的でした。
いわゆる「赤字を入れる」というやつですね。
校正のときによく使われていた言葉に「トル」や「トルツメ」というのがあります。
これは、
- 「トル」=その部分を削除する
- 「トルツメ」=削除して、さらにスペースも詰める
という意味です。
専門用語っぽいですが、当時はみんな当たり前のように使っていました。
今はPDFに赤字を入れる時代
最近では、紙に出力することはぐっと減りました。
PDFデータをタブレット(たとえばiPad)やパソコンで開き、そこに直接赤字を書き込むスタイルが主流です。
データで管理できるので、修正のやりとりもスムーズ。
ペーパーレスなので、環境にもやさしいですよね。
私は普段、PDFをiPadに取り込んで、Apple Pencilで赤字を入れています。
紙からタブレットにカタチは変わりましたが、手書きは相変わらずです。
なぜか手で書いたほうが校正に集中できるんですよね。
あと、校正に慣れるまでは、あえて原寸大の用紙にプリントしてみるのもおすすめです。
実際の仕上りイメージとして、文字の大きさや全体のバランスを見るのにいいですよ。
初校は原寸大の紙で、それ以降はタブレットやPCでと使い分けてもいいですね。
校正記号は今どうなっている?
「トル」や「トルツメ」みたいな専門用語、今でも印刷業界やベテランのデザイナーさんたちの間では使われています。
でも最近は、よりわかりやすい指示を求められることが増えてきました。
たとえば、
- ここの文章を削除してください
- ここからここまで消して、前後を詰めてください
と、誰にでも伝わるように書くスタイルです。
特に、デザインを初めて発注する方や、校正に慣れていない方にとっては、専門用語よりも具体的な説明のほうが安心ですよね。
校正ツールもいろいろ増えています
最近では、「Brushup」や「AUN」など、オンラインで校正指示を出し合えるサービスもあります。
チームでの共有がしやすかったり、修正履歴が管理できたりと、便利な機能がたくさん。
もちろん、チラシ1枚や小さなパンフレット制作くらいなら、「PDFに直接赤字を入れてメールでやりとり」くらいのシンプルな方法でも、十分だと思います。
まとめ:大事なのは「伝わる赤字」
どんなに校正のやり方やツールが変わっても、一番大事なのは「伝わる赤字」であること。
・誰が見ても、何をどう直すかがわかること
・無駄な修正を防いで、スムーズに仕上げること
これが校正の基本です。
紙でも、タブレットでも、クラウドツールでも。
自分たちに合ったやり方で、正確に、そして気持ちよく進めていきたいですね!